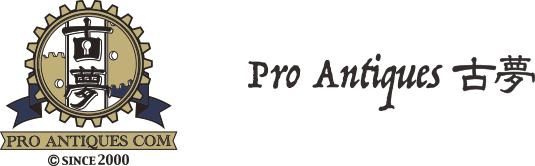- ホーム
- アンティークの器の魅力「窯きず」
アンティークの器の魅力「窯きず」
アンティークの器を見ていると、「窯きず」といって
「焼成時にできた傷(つまり窯の中で出来た傷)」
を持つ器に出会うことが多々あります。
陶磁器の場合、現代ではガス窯や電気窯で焼かれることがほとんどですが
江戸時代や明治時代は「登り窯」で焼かれていました。
登り窯は連房式登窯などいくつか種類がありますが、
土やレンガでできた窯に薪で火を起こし、
1000度以上の高温で熟練の職人たちが約60時間、
丸二昼夜かけて焼き上げる途轍もない窯です。
窯出しには急速な冷却により割れることもある為
慎重に慎重に焼成時と同じくらいの時間が
かけられました。
それほどの努力の上で焼き上げられた陶磁器たちは、
様々な個性を持って生まれます。
窯の天井が剥がれたり、
窯の中を舞う薪の灰が付着した時に出来る
「ふりもの」は登り窯で焼いた証拠でもあります。
アンティークの世界では、傷として扱われない
「窯きず」があり、
その個性を景色として楽しむ事ができるのです。
ー 注意 ー
このように窯きずを個性として楽しまれる方も多いですが、
その一方で気になられる方もおられます。
現代の大量生産品と違い、一つ一つ手作りの為歪みなども有り、
絵付けや形も「全て違います」。
例えば、在庫が「5」になっている商品であっても、
その「5」は全て少しずつ違います。
ご購入の際は、必ず説明文をご一読いただきまして
商品写真をご確認していただき、
ご理解ご納得の上でご購入くださいます様お願い申し上げます。
弊社取扱商品には、以下の様な「窯きず」があるものが含まれます。
あらかじめご了承くださいませ。
(以下窯きず一例)
「ふりもの」


「釉切れ」

「むしくい」

「かんにゅう」

「釉ムラ」(高台部焼き台くっつきによる削げ)

「歪み」・「ふりもの」

縁に「ばり」

「しわ」

「型あと」

「気泡」